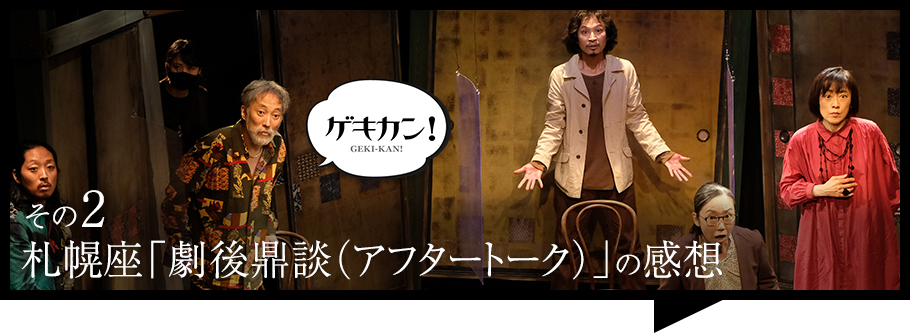
禁じられたことをあえてやるいたずらっ子のような戯曲だ。
コロナまっただなか。集まるな、話すな、近寄るな。演劇だけでなくすべての活動が制限されたときに、斎藤歩は想像力を羽ばたかせた。自由で変で風変わり。活動を制限するなら脳内ではとことん好きにやるぞと言わんばかりに。
キーボードを叩きながらおかしな妄想がぶくぶくふくらみ、物語がいつしか暴走をはじめたとき、彼はきっとうれしかったに違いない。自分を縛るものはなにもない。想像力はどこまでも自由なのだ。
札幌座『劇後鼎談(アフタートーク)』。ご存じの方も多いと思うが、この劇の作・演出、出演も予定していた斎藤歩は亡くなった。だけど最後にこんなに笑えて、こんなにふざけた、自由で変な作品を残していくなんて。すてきじゃないか。
とある劇団の舞台が終わりアフタートークがはじまる。アゼルバイジャンの戯曲を翻訳した舞台だったらしい。ちょっと堅物の演出家と、アクションもできる主演女優と、音楽担当のミュージシャンと、極めてまじめな司会者。そこに翻訳家も加わる。
異文化交流のような、ちぐはぐな笑いが随所にありトークは進んでいくが……ここからがこの戯曲の、この舞台のおもしろいところだ。なんとも奇妙な、ほんとうにおかしな展開になっていくのでぜひぜひ「ジョブキタ北八劇場」に行って生で体感してほしい。ネタをばらしてしまうのはもったいない。知らないで大いに驚いて、戸惑って、笑ってほしい。
僕は途中から安部公房の小説やその中のSF作品を思い出したし、なにより斎藤歩の代表作のひとつ『亀、もしくは・・・。』。そう、あんなヘンテコですばらしい戯曲を書く人だ。一筋縄でいくわけがない。
観る者をあっという間に不可解な非現実の渦に落としたと思ったら、意外とそこは居心地がよく、かといってそこに長居をしていいのかどうか迷ってしまう。そんな不安定で楽しい場を舞台上に出現させる。さすがだ。
それにしても今回の、僕たち観客がぽかん……となるあの瞬間。たまらないね。どんどん正気の輪郭が削られていく感じ。くせになる。
さてこの劇は、客席にいる我々もアフタートークを聴いている客という体裁なので、おかしくなっていく場の目撃者であり体験者であり共同制作者でもある。ときに笑い、ときに困惑し、ときに拍手する。この一体感が気持ちいい。
これが斎藤歩がつくろうとしていたものなんだろう。あの閉塞感の中で、制限された活動の中で、想像力を羽ばたかせ、ヘンテコな物語で舞台と客席をひとつにしようとした。
今日、それは成し遂げられた。北八劇場でそれは生まれた。
斎藤歩だけの舞台じゃない。役者、スタッフ、観客もふくめ、僕たちはひとつになって劇をつくった。すてきな舞台だった。僕好みだ。ヘンテコなのがなおいい。ヘンテコなのに精緻だ。
終演後、観終わった客たちが劇場を出て札幌の街に散らばっていく。今日この舞台の感情をたずさえて。消えない思いとともに。
僕も街を歩いた。いままでの作品を思い出しながら。ありがとうございました。
劇場へと足を踏み入れるとそこは、終演後だった。
と書くと、まるで遅刻をしてしまったように思えるけれど、もちろん違う。
札幌座「劇後鼎談(アフタートーク)」は、そのタイトル通り、演劇公演の終了後に行われるアフタートークが舞台だ。
直前まで仕事をしていた私は、「開演ギリギリになるかも」と早足でジョブキタ北八劇場へと向かったが、結果として17時半の開場に余裕で到着。これが心底「よかった!」と思えたのは、劇場内の光景のせいだ。
というのも、劇場内に入ると舞台上には刺さったままの日本刀、散らばる和服や帯、そして血飛沫の残る襖があり、「一体どんな惨劇が・・・」と突っ込みたくなる有様。
その誰もいない惨劇後の舞台を前に、客席で談笑する人たちのほのかなザワザワ感が、まさに本番を終え、アフタートークが始まるまでの少しの間のブレイクタイムのような空気で、待ち時間すら「あぁ、もう始まっている!」と思わせてくれるのだ。
やがて、襖の奥から現れたスタッフが惨劇の跡を片付け始め、舞台上に椅子を置く。山木翔平さん演じる庭野が現れてギターを爪弾き、スタッフは粛々と片付けを進めて、最後にパーテーションを設置する。透明の板が役者同士を分断するその様は、あのコロナ禍で幾度も見た光景だ。
ほどなくして、進行役と役者、演出家が登場し、途中で戯曲を翻訳したアゼルバイジャン人も登場。劇団「シュリンプスラング」の「未開封のアロワナ」のアフタートークはやがて、想像を超えた展開へと進んでいく−−。
と、書いている今も、一体なんだんだ!と笑いが込み上げてくる。怒りや皮肉を内包しながらも、とことん笑えて面白い。
あぁ、なんて楽しい!なんて常軌を逸したヘンテコさ!なんて新感覚!斎藤歩さん・・なんて作品を作ったんだ!
演劇はいつも、私たちをどこかに連れ出してくれる。
時には懐かしいあの頃に、あるいはまだ見ぬ世界に。
客席に座る私たちの意識は大きく羽ばたいて、違う次元へと導かれていく。
「劇後鼎談(アフタートーク)」も、それはもう、想像を越えた遥か彼方まで我々を連れ出した。いや、連れて行ってもらったというより、観客の拍手、驚き、戸惑いも、全てが舞台の一つとして生かされていくので、もはや、共犯関係のように共に遥か彼方へと飛び出して行った、という感覚の方が近いのかもしれない。
あの閉塞感に満ちたコロナ禍で、観劇することは救いだった。
不要不急と言われたけれど、観劇に行くという行為を選択できる自由は、決して不要ではない。演劇のみならず、あらゆる文化芸術を選択できることは人間が人間として生きていくためにかけがえのないことだと思っている。改めてあの時代、試行錯誤の中で、劇場の扉を開け続けたあらゆる関係者たちに感謝をしたい。
椅子に座ったままの役者たちは、動きとしては「静」だが、身体から発さられる言葉は限りなく「動」。身体的な言葉と共に躍動する様は、役者陣の力量を改めて感じさせてくれた。
そうして、ミクロからマクロへと物語が拡大していくその展開に覚えた感覚は、もはや、抑圧からの解放だ。
ラスト間近の、あそこからあれが出てきた時は、そうした謎の開放感、そして達成感すら覚え、笑いながらも、なんだか無性に感動してしまった。
――なんのこっちゃ!と思う人は是非とも劇場に。想像を超える遥か遠くに接続する体験がきっと待っています。
初演された2021年8月に、ぼくはZOOでこの芝居を観た。
あの時はコロナ禍真最中で、舞台に吊られたアクリル板も状況から仕方ないものとして自然と受け入れていた。もうあまり記憶にないけれど、席も間隔が開けられて人影まばらに座っていたように思う。
今回、北八劇場の客席から開演前の舞台のセットを見ながら、当時のことを思い出す。
文化活動が「不要不急」と言われたことは、あらゆる文化活動にたずさわる人々にとって不条理なものと感じられた。
あのころを思い出すと、いまも怒りをおぼえるが、同時にコロナに怒ってみてもしかたがないし、「不要不急」などと言った人たちに怒ってみてもどうにもならない。
演劇はおそらく一番抑圧された活動のひとつだったろう。
そんな混乱した状況の中で、この劇は初演された。
でもぼくはこの作品自体が、時代への警鐘として演じられているということに実は気づいていなかった。コロナだからこういう形でやらざるを得なかったのだろうと漠然と思っただけだった。
今回、ようやく気づいた。この芝居は、パンデミックという時代を生きる人々に、リアルタイムで突き付けられた強烈な諧謔だった。
舞台には「今終わった芝居」のセットが残されている。劇団シュリンプスラングの「未開封のアロワナ」という劇。舞台上の小道具などを舞台監督が片付ける何気ない終演後の作業風景から、芝居が始まる。
ギタリスト(山木将平)がギターの演奏を始める。
椅子が四つ配置され、席の間にアクリル板を一枚一枚吊るしてゆく。
初演の時には、ああそういうことをしなければ上演できないんだなぁ、と思ったことが今回も行われる。
初めてこういうことがこの作品で必須だったのだと気づく。そしてあの時仕方がないと思ったことが、いまではとても異様に見えることの落差を感じた。
アフタートークというのは、終演後に舞台に演出家や役者が登場して裏話などしたり、客席と交流したりする趣向で、つまり虚構の世界から戻ってきた役者たちが素顔を見せる場なのだが、この劇はそこから始まるのだった。
つまり、虚構が入れ子になっている。
ぼくら観客は、いまさっきまで演じられていた劇を見た後という前提で客席にいることになる。アフタートークの司会者が何か言ってそれに拍手をするぼくらは、劇の中で必要な演技のひとつを演じていることになる。なんとなく不自然な感覚に襲われてしまった。
ギタリストの後に、演出プロデューサーでこのトークの司会の小本沙季(磯貝圭子)、演出家の渡会響(納谷真大)、主演の反町雲母(西田薫)が現れる。
小本の司会でトークが始まり、それぞれのこれまでの演劇歴のようなことを語り合うのが妙にリアルで、納谷さんの演じる渡会が斉藤歩さんのように見えてならなかった。西田さん演じる反町との会話が、歩さんと西田さんの会話のようにさえ見えてきた。
ぼくはこの劇の導入部にあたるゆるいトークの場面がとても好きだ。最後までこの調子でやるという手もあったんじゃないか、とさえ思うほどだ。
パロディの笑いにあふれている。
中盤あたりで、ひとつ空いていた席に「未開封のアロワナ」の原作を日本語に訳したエルヌール・アフマドフ(明逸人)が現れて座る。
ここから劇は奇妙な食い違いの道に進みだしてゆく。
劇中、扉に激突し血まみれになった女の頭から黄色いハイビスカスが咲くという意味不明の場面が、アフマドフの誤訳のせいで生まれたことがわかり、狼娘のサフラを演じた役者小恋(熊木志保)が引っ張り出されてその場面を演じるシーンは大爆笑だった。
そうしてトークが進むうちに、なにやらしだいにオカルトめいた話に変わってゆく。
アフタートークがその枠を中から壊しはじめて、あり得ない世界へと暴走してゆく。
あり得ない感じというのが、実は新型コロナ禍と呼ばれる世界的な状況の異常さというもののアナロジーであるのを、いまごろになって気づいた。
この劇は、何かを説明したり演説したりする類のものではもちろんない。
ただ、4年前の初演時、ぼくらが経験した奇妙な時代。そのときぼくらがどうやって自分を保とうとしたか、それが強く関係する劇だ。
それはコロナの時代だけの問題ではないことに気づかされる。
昨年11月に観た「民衆の敵」にも共通するテーマがそこにあった。
裏側に悲劇が同居する不条理喜劇。そこに現在と予言的未来が浮かび上がり、警鐘が鳴り響く。
これは演劇人・斉藤歩の遺言だ。
劇が終わって北八劇場の廊下に出たとき、そこに歩さんがいつものように立っているような気配があった。ごつっとした手の感触を思い出した。
この日、歩さんは北八劇場に確かにいた。